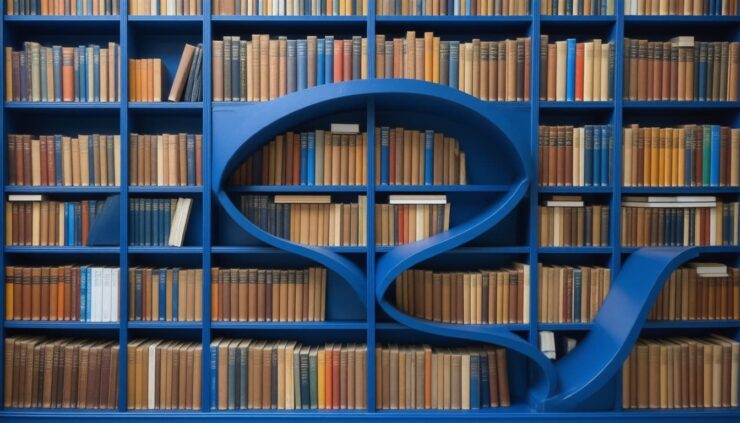これは、静かなる誓いの話だ。語るより、刻むもの──
「何が正解か、もう分からない」
そうつぶやいたあなたの目には、疲れと焦りが交錯していた。
情報は溢れ、選択肢は無限にある。
けれど、どれを選んでも、確信は得られない。
「これでいい」と思いたいのに、心のどこかで──「本当にこれでいいのか」と問いが残る。
正解のない時代。
そこを生きるわたしたちに必要なのは、
正しさではなく、納得できる選び方なのだと、わたしは思う。
目次
正しさではなく納得を選ぶ
「最適解」より「納得解」で生きる
「正しい決断をしたい」と願うのは、当然だ。
けれど、その正しさは、誰が保証してくれるのか。
状況は変わる。社会も変わる。
昨日の最適解が、今日の足かせになることさえある。
だからこそ、今の時代に必要なのは、
「納得して選ぶ力」だと、わたしは考える。
外からの正解ではなく、
「この選択を自分で引き受けられるかどうか」──
その問いこそが、決断の軸になる。
「どんなリスクなら背負えるか」が判断基準になる
どんな選択にも、リスクはつきまとう。
問題は、そのリスクを他人の基準で測ってしまうことにある。
他人にとって大きな失敗でも、
自分にとっては「経験の一部」に過ぎないかもしれない。
反対に、他人には些細に見える決断でも、
自分にとっては「信じた誇り」を損なう選択かもしれない。
──だから、わたしは問いたい。
「あなたは、どんな痛みなら受け入れられるか?」
「何を守るために、それを選ぶのか?」
納得のある選択とは、リスクを自らの手で抱きしめる覚悟から始まる。
判断力を支える前提の点検
前提が変われば、結論も変わる
どんなに論理的に考えても、
「前提」がずれていれば、その結論は誤ったものになる。
仕事、家庭、未来像──
これまで当然だと思っていたことが、
実は今の自分には合わない前提で組まれていたとしたら?
──正しさとは、構築物だ。
だからこそ、定期的に前提を点検する視点が必要なのだ。
「本当にそうか?」と自問する技術
- 「今の会社を辞めたら人生が終わる気がする」
- 「転職はリスクが高いものだ」
- 「やりがいなんて贅沢だ」
──それは本当に事実だろうか?
それとも、誰かから受け取った「思い込み」ではないか?
自分の判断を信じるために必要なのは、
問い直す力であり、
自分に疑問を差し出せる勇気だ。
わたしは思う。
決断の誠実さとは、「疑う力」の上に成り立っている。
選びきれぬ自分を、責めずに受け入れる
選べない時期も、決断の一部
選べない時間は、無意味ではない。
それは「怠慢」ではなく、内なる整合性を保とうとする抵抗だ。
誰かのようにスパッと決められなくてもいい。
それは、あなたが「自分の選択に誠実でありたい」と願っている証だから。
焦る必要はない。
人生の中には、「決めかねることが、最大の決断である瞬間」もある。
だから──
選べない自分に失望するのではなく、
その選ばなかった時間もまた、自分の意思の一部だったと認めてほしい。
決断とは、向き合い続けること
わたしは思う。
決断とは、「一度だけの選択」ではない。
それは、問い直し、立ち止まりながら、何度でも手を伸ばす行為だ。
進んでは迷い、振り返ってはまた歩く。
そのくり返しの中でしか、本当の納得にはたどりつけない。
もし、今あなたが「選びきれずに立ち尽くしている」のなら──
それは、あなたが軽率な決断ではなく、誇りある決断をしたいと願っている証拠だ。
選ぶことに怯えず、
選べない自分を否定せず、
選び直す力を信じて──
いま、あなたが立っているその場所にも、
静かに、旗は立てられている。