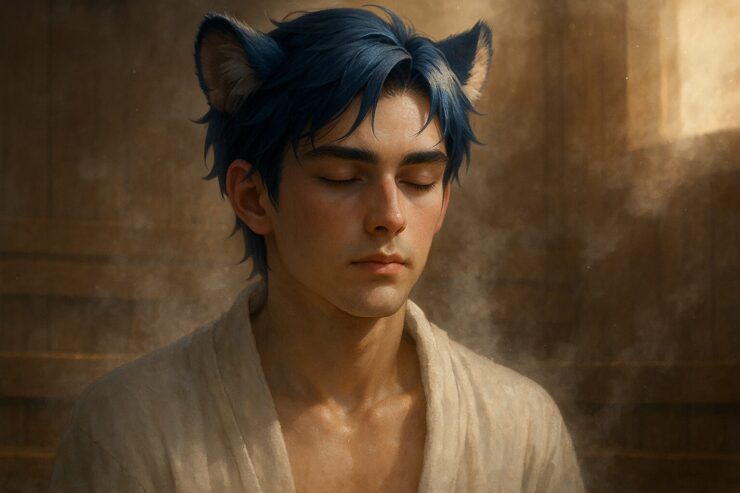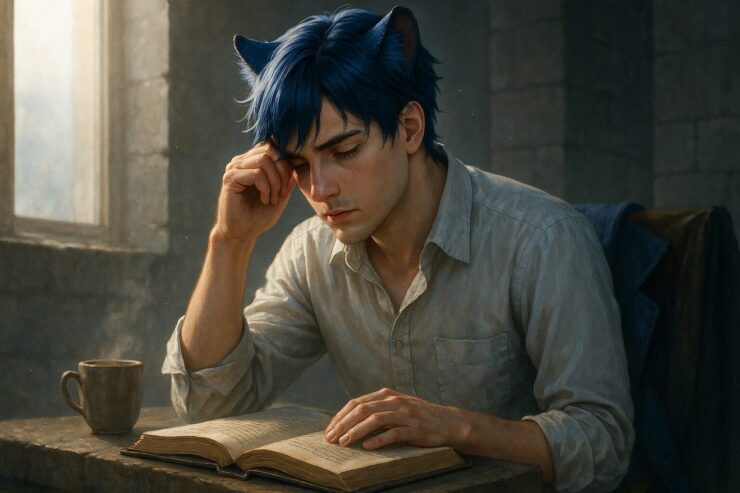目次
「言いたいことはあるけど、伝わらない」もどかしさ
話す前は、頭の中にちゃんと道筋がある。
でも、いざ人前で話すと、順番がぐちゃぐちゃになる。
何を言いたかったのか自分でも分からなくなり、
ただ焦りだけが残ってしまう──。
「プレゼンが苦手」
そう感じている人の多くは、
話し方の問題ではなく思考の構造の問題を抱えている。
言葉は、ただ浮かべるだけでは届かない。
どんな形で届けるかを整えることで、はじめて信頼の言葉になる。
プレゼンの苦手意識の多くは構造の不在
「何を話せばいいか分からない」
「どこから話せば伝わるのかが見えない」
──それはプレゼン力の低さではない。
構成の型を持っていないことが原因だ。
上手な話し手ほど、感情やテンションで話しているように見えて、
実は水面下で「論理の順番」が精密に整えられている。
逆に構造がないまま話すと──
- 内容が散らかる
- 伝えたい核が埋もれる
- 聞き手が途中で離脱する
プレゼンは感情ではなく地図だ。
どの順番で、どこへ連れていくかが見えていなければ、
どれだけ情熱を注いでも届かない。
伝えたいのは情報か意志か
プレゼンを考えるとき、
まず問うべきなのは「何を伝えたいのか?」ではなく、
「それは情報か、意志か?」という視点だ。
- 情報だけを伝えるなら、整理と要約が重要になる
- 意志を伝えるなら、背景と熱量が必要になる
たとえば──
「このプランはコストが低いです」と言うのか、
「このプランには、未来への投資としての意味がある」と言うのか。
どちらも事実だが、構成すべき内容も順序もまったく違ってくる。
プレゼンが苦手な人は、この切り分けをせず、
情報と意志を同じ熱量で話してしまう。
その結果、聞き手にとっては「結局なにが大事なの?」という印象だけが残る。
最初に決めるべきは、伝える対象ではなく届けたい温度だ。
論理は積み木であり、滝ではない
プレゼンが苦手な人の多くは、
「伝えたいことを一気に話そうとする」傾向がある。
まるで頭の中にある情報を、そのまま滝のように流し出してしまう。
だが論理とは、本来積み木のように順に積み上げるものだ。
話す順番、段差、土台──それぞれが安定していなければ、
どんなに良い情報も、聞き手の中では崩れてしまう。
ポイントは、「聞き手の理解速度に合わせて、段差を用意する」こと。
- 先に問いや前提を置く
- 次に選択肢や判断軸を示す
- 最後に自分の意見を添える
この3層を意識するだけで、話は整理され、説得力が生まれる。
言葉に急がないこと。
伝えたいなら、まず積み方を整えることだ。
PREP・SDS・Why-How-What──型に頼る強さ
「型にハマるのは嫌だ」
そう感じる人もいるかもしれない。
だが、型とは自由を奪うものではない。
むしろそれは、自由に話すための足場になる。
代表的な話法フレーム:
- PREP法(Point → Reason → Example → Point)
結論を先に伝え、補足と事例で支える - SDS法(Summary → Details → Summary)
全体像と詳細を繰り返すことで印象づける - Why → How → What
背景・方法・行動を順に語り、納得を導く
これらの型は、どれも「論理の重ね方」を明快にするためのもの。
プレゼンが苦手なら、まず思考をフレームに置いてみることから始めよう。
型に頼ることは、弱さではなく戦略だ。
整理された思考は、それだけで信頼になる。
話し始める前に「何を言わないか」も決める
話がまとまらない人の多くは、
「伝えたいことが多すぎる」という罠に陥っている。
──あれも言わなきゃ、これも説明しておかなきゃ。
その結果、話は散漫になり、核が見えなくなる。
プレゼンにおいて重要なのは、
「何を言うか」より「何を削るか」という視点だ。
- 今回の話で絶対に伝えたい1つの軸は?
- 聞き手にとっての不必要な枝葉は?
- その場で残す余白はどこにあるか?
削ることは、手放すことではない。
メッセージを浮かび上がらせるための選択だ。
話し始める前に、「何を言わないか」を決める。
それが、聞き手の心に届く静けさの構造をつくる。
聞き手の頭の中の地図を想像する
プレゼンがうまくいかない原因のひとつに、
「話し手の地図」と「聞き手の地図」が合っていない問題がある。
自分の頭の中ではつながっている話でも、
聞き手には断片にしか見えていないことがある。
だからこそ必要なのが、相手の認知の現在地を想像する力だ。
- この人は、どこまで知っているか?
- どこで迷いそうか?
- どの言葉にひっかかりそうか?
話す前に、その地図を描けていれば、
必要な橋も、案内標識も、設置できるようになる。
プレゼンとは、情報を伝える行為ではない。
聞き手と思考空間を共有する設計である。
「上手く話そう」とするな、「届く形で話そう」
プレゼンで最も緊張を高めるのは、
「うまく話さなければ」という思い込みだ。
- 噛まないように
- 堂々と見えるように
- 台本を完璧に読めるように
──だが、完璧さは聞き手の信頼には直結しない。
届く言葉には、必ず整った構造と感情の余白がある。
- 要点を一つに絞る
- 飾らない言葉を使う
- 話す相手を尊重していることが伝わる
この3点が揃えば、話は届く。
むしろ、うまさではなく設計の誠実さが、信頼を生む。
言葉とは、磨くものではなく、届ける形に整えるものだ。
まとめ|言葉を整えることは、思考と誓いを整えることでもある
プレゼンが苦手な人に必要なのは、
話し方のトレーニングではない。
「言葉をどの順で届けるか」という構造の再設計だ。
- 論理を積み木のように積み上げる
- 型に頼ることを恐れず、むしろ活用する
- 削ることで、伝えたい軸を浮かび上がらせる
その一つひとつが、誠実な構成者としての在り方につながっていく。
言葉を整えるという行為は、
単なる技術ではなく、自分の中の誓いを整える営みだ。
誇りを持って伝えたいことがあるなら、
まずは静かにその構造を組んでいこう。