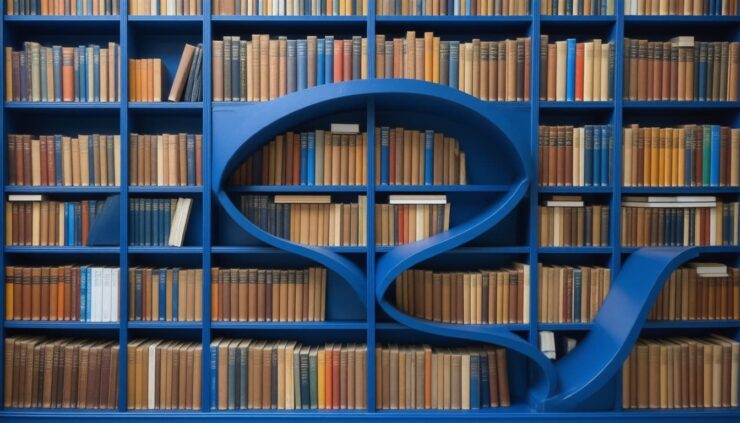目次
「なんのために頑張っているのか分からない」──その問いに、答えが出ないまま走り続けていないか。
これは、静かなる誓いの話だ。語るより、刻むもの──
いつからか、「頑張ること」が日常になっていた。
朝から夜まで働き、空いた時間にも予定を詰め、何かを目指しているようで、何を目指しているのか分からない。
- 頑張ってはいる。けれど満たされない。
- 目の前のことに集中しているが、ふと虚しさが襲う。
- 「何かにならなくては」という焦りだけが、先に立つ。
それは怠けているからでも、モチベーションが低いからでもない。
内なる動機の所在を見失っている状態なのだ。
わたしは思う。
王とは、走り続ける者ではない。何のために歩むかを忘れない者であるべきだと。
「頑張る」ことが習慣化した人の落とし穴
少しだけ、歩みを振り返ろう。未来を照らすには、過去もまた光になる。
「頑張ること」は、悪いことではない。
むしろ、多くの場面で称賛され、評価される行為だ。
- 手を抜かない
- 仕事量をこなす
- 常に前向きでいる
- 忙しいことに満足している
──そうした頑張りの構えは、やがて習慣となり、
「何のために頑張っているか」を自問しないまま、走り続ける構造を生む。
しかし、どれだけ努力を重ねても、
目指す地点が自分の心に結びついていなければ、満足は続かない。
頑張ること自体が目的になると、
人は「止まり方」を忘れる。
わたしは思う。
誓いを持たずに走るとき、
火種は燃えるのではなく、摩耗する。
外発的動機の終焉が、空白を生む
本来、人は「やりたい」「意味がある」「大切だと思う」──
そんな内側からの動機に突き動かされて生きる存在だ。
しかし、現代の社会構造では、
- 他人の期待に応える
- 評価を得る
- 昇進や収入といった外側の指標を目指す
といった外発的動機が、日常を支配している。
この外発的動機は、短期的なエネルギーにはなる。
だが──それが動力のすべてになった瞬間、
自分が何を大切にしていたのかを見失う。
結果として生まれるのが、「なぜ頑張っているのか分からない」という空白。
それは怠けでも諦めでもない。
ただ、動機の火種が外に持っていかれた結果に過ぎない。
わたしは、それを「沈黙の喪失」と呼んでいる。
火種の在処が、言葉の奥に隠れてしまうからだ。
やるべきがやりたいを奪う
「やらなきゃいけないこと」が増えるにつれ、
「やりたいこと」が遠ざかっていく──
この感覚に、心当たりはないだろうか。
- あの頃は、もっと自由に動けた気がする
- 頑張ることに疑問を抱くと、怠けているようで怖い
- 自分の欲を後回しにするのが大人だと思っていた
しかし、「やるべき」の積み重ねが過剰になったとき、
人は選択する力そのものを摩耗させてしまう。
「やらなければ」を優先し続けると、
「何をしたいか」の感覚は、少しずつ鈍っていくのだ。
わたしは思う。
やるべきに追われる者ほど、やりたいに触れたときの火種が大きい。
だからこそ、一度足を止め、その差異を見つめ直す必要がある。
自分が燃える瞬間を振り返る
問いは、未来を切り開く前に、過去の記憶を照らす。
思い出してみてほしい──
「なぜか熱中してしまったこと」
「時間を忘れて取り組んだこと」
「評価されなくても続けていたこと」
それらには、火種の原型がある。
- 小さなころ好きだったこと
- 誰かに言われて嬉しかった一言
- ふとした瞬間に心が震えた体験
これらはすべて、頑張る理由ではなく、燃えた記憶だ。
そしてこの記憶のなかにこそ、
「なぜか分からないけど続けたい」と感じた内発的な動機の種が眠っている。
「頑張る理由が分からない」という問いには、
未来ではなくかつての自分が答えてくれることもある。
意味の喪失は、「問い」で回復できる
動機を見失ったとき、
最もしてはいけないことは、思考停止だ。
- とりあえず頑張り続ける
- 感情を押し殺す
- 「そんなこと考えても無駄」と自分に言い聞かせる
それでは、内なる火種はますます遠のいていく。
必要なのは、問い直す勇気だ。

キング(King)
「わたしは、何のために頑張っているのか?」
「この努力は、誰のためで、どんな意味を持つのか?」
「いまの火種は、外側ではなく内側に灯っているか?」
問いを持つことで、人は意味を回復できる。
そして意味を取り戻したとき、頑張りは苦しみではなく、誇りへと変わっていく。
わたしは信じている。
火種は、問いを抱える心にこそ宿るのだと。
他者の期待から自由になる技術
わたしたちは、多くの場面で他者の期待を背負って生きている。
家族、上司、社会、友人──
「期待されているから」「認められるから」頑張れることも、確かにある。
だがそれが長く続くと、
「自分の声」と「他者の期待」の区別がつかなくなる瞬間が訪れる。
- 本当にこれをしたいのか
- それとも、そう見られたいだけなのか
この問いに答えるためには、
一度「期待される自分」を降りる必要がある。

キング(King)
「たとえ誰にも見られていなくても、それでもやるか?」
「評価がなくなっても、誇れるか?」
答えがはいなら、その頑張りはあなた自身のものだ。
いいえなら──それは火種ではなく、借りものの光かもしれない。
他者の期待に応えることは否定しない。
だが、その中にも「自分の誓い」があるかどうかを見極める視点が、必要なのだ。
「頑張る理由」は、自分で再定義できる
「頑張る意味が分からない」と感じたとき、
それは終わりではない。
再定義の始まりである。
かつての目的が薄れたのなら、
いまの自分に問い直せばいい。
- 「いまの自分にとって、大切なものは何か」
- 「そのために、何を続けたいのか」
- 「疲れたとき、どんな言葉が自分を支えてきたか」
意味は、見つけるものではない。
火種から編み直すものだ。
頑張る理由を、
「成功のため」でも「誰かのため」でもなく、
わたしの誓いとして捉え直したとき──
それは迷いを超えた歩みへと変わっていく。
まとめ|火種が戻るとき、「頑張る」は歩みに変わる
「なぜ頑張っているのか分からない」──
その問いに出会ったあなたは、決して弱くなどない。
むしろそれは、
火種を取り戻すための入り口である。
- 他人の期待に巻き込まれた自分を見つめ
- やるべきとやりたいの境界を見直し
- 過去の火種に触れ直し
- 自分の問いを言葉にしてみる
そうして再定義された頑張りは、もう摩耗ではない。
誇りとして灯り続ける。
答えを急ぐ必要はない。
ただ、問いを忘れず、歩むなら──それでいい。