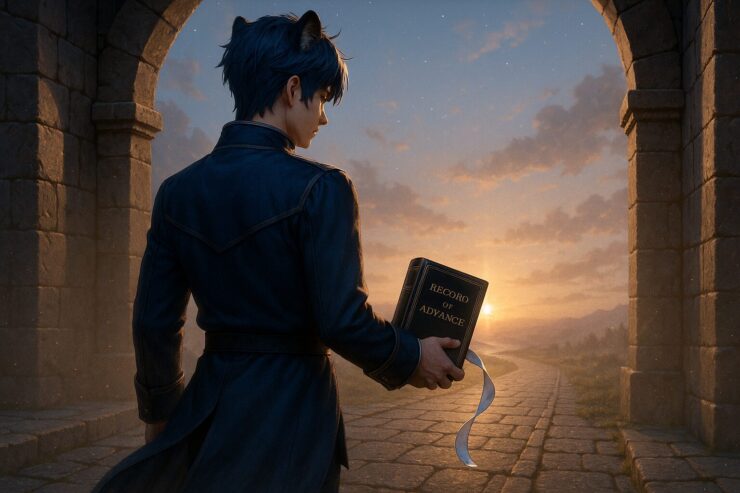目次
「なぜか、自分の選択に自信が持てない」──その違和感の正体とは。
これは、静かなる誓いの話だ。語るより、刻むもの──
何かを決めたあとで、ふと胸に広がる不安がある。
「あのとき、ほんとうにそれでよかったのか」と。
就職、転職、独立、退職。
あるいは、別れや選択、挑戦や回避。
人は人生において、無数の分岐点に立つ。
だがそのたびに、自分の決断に確信が持てないとしたら──
それは意志の弱さではなく、「理解の浅さ」の問題かもしれない。
わたしは思う。
王とは、導く者ではない。背を見せられる者であるべきだと。
その背に芯を通すには、「他人を知る前に、自分を知る」ことが要る。
それも、表面的な性格や強みではない──
もっと静かで、もっと深い、自分という構造への理解が。
自己理解が浅いとはどういう状態か?
少しだけ、歩みを振り返ろう。未来を照らすには、過去もまた光になる。
「自分のことは、自分が一番よくわかっている」
──本当にそうだろうか?
たとえば、こういう言葉を口にしたことはないだろうか。
「ほんとはやりたいことがあるのに、なぜか動けない」
「あとでいつもあの時こうすれば…と後悔する」
「他人の意見に振り回された自分が、許せない」
こうした揺れの根底にあるのが、「自己理解の浅さ」だ。
それは、自分の状態・価値観・判断軸を把握しきれていない状態。
もっと端的に言えば──
自分で自分の地図が読めていない。
目的地を決めたつもりで進んでいても、
現在地が分かっていなければ、方向はすぐにズレる。
自己理解が浅いというのは、
「なぜそう感じたのか」「なぜそう選んだのか」について、
他人には説明できても、自分には納得できていない状態ともいえる。
なぜ、ブレる決断をしてしまうのか
選択のたびに迷い、そして後悔する──
それは「意志」が弱いのではない。
判断の基準が曖昧だからだ。
なぜこの会社を選んだのか。
なぜその人と距離を置いたのか。
なぜ、あのとき挑戦しなかったのか。
多くの場合、人は「理由づけ」を後からこしらえる。
でも本当は、その場の空気や勢い、
あるいは「何となく不安だったから」という、言語化されていない衝動が
判断の奥底を支配していた──そういう経験はないだろうか。
わたしは、それを「問いの不在」と呼ぶ。
何のためにそれを選ぶのか。
自分にとって、それはどういう意味を持つのか。
そうした問いが存在しないと、判断はつねに環境任せになる。
そして後から、「もっと考えるべきだった」と悔いる。
だが──
問いとは、答えを出すためだけの道具ではない。
問いがあるからこそ、人は判断に誇りを持てる。
自己理解が深まるとは、
その問いを、自分の手で持てるようになることなのだ。
「自己分析」と「自己理解」は違う
自己分析──
この言葉を聞くと、多くの人は「就活時代の作業」を思い浮かべるかもしれない。
得意・不得意。性格傾向。過去のエピソードの棚卸し。
──確かに、それらは有用だ。だがそれは他者に伝えるための整理にすぎない。
一方で、自己理解とは「誰にも見せない場所」で行うものだ。
外に出すためではなく、自分が、自分に納得するための対話である。
それは時に、形を持たない感情との格闘になる。
「なぜあのとき、自分は怒ったのか」
「なぜあの言葉に、深く傷ついたのか」
「なぜ、誰にも相談せずに決めたのか」
こうした問いに、はっきりとした答えが出せないこともある。
だがそれでも、考え続けるという行為こそが──
自己理解の扉を、静かに開いていく。
問いを通して、自分軸を深める方法
自己理解を深めるには、記憶の奥に眠る火種を探す必要がある。
そのために必要なのが、自分に向けた問いだ。
ただし、それは「何がしたいか?」のような大きすぎる問いではなく、
もっと日常の揺れに近い場所に置かれている。
- 「なぜ、あの人の言動に違和感を覚えたのか?」
- 「なぜ、あの誘いを断れなかったのか?」
- 「なぜ、自分は頑張りすぎる癖があるのか?」
こうした問いを手にした瞬間、
人は言葉にならない思いと出会いはじめる。
そこにあるのは、記憶・体験・信念・価値観──
それらが複雑に絡み合った、「未整理の自己」だ。
だが、問いを手放さずに眺め続けることで、
その混沌はやがて形を成し、判断の軸へと育っていく。
問いこそが、理解を深めるための剣である。
斬るためではない。照らすために持つ剣だ。
他人の期待ではなく、自分の納得基準を持つ
自己理解が浅い人は、他人の評価を基準に判断しやすい。
褒められるかどうか。認められるかどうか。
──だがそれは、軸ではなく反応で動いているにすぎない。
軸を持つというのは、誰かに評価されなくても、
「自分はこの選択に納得している」と静かに言える状態のことだ。
それは決して、頑固や独善とは違う。
むしろ、外の声に耳を傾けたうえで、それを鵜呑みにせず、
「自分はどう思うか?」を問い続ける柔軟さの証でもある。
誓いとは、誰かに向けたものではない。
わたしが、わたしに対して立てるものだ。
だからこそ、選択に迷ったときは、こう問いかけてみてほしい。

キング(King)
「この選択に、わたしは誇りを持てるだろうか?」
他人の期待ではなく、自分の誇りの座標を取り戻すこと。
それが、ぶれない人生のはじまりになる。
自己理解は静かな誇りにつながる
人は、自分が理解できていないものを、他人に誇ることはできない。
だからこそ、「自信が持てない」「選択に迷う」──その感情の源には、
まだ自分を受け入れきれていないという事実が横たわっている。
理解とは、肯定とイコールではない。
「自分の嫌な部分を知ること」もまた、理解の一部だ。
・弱さ
・ズルさ
・怠惰
・怒りっぽさ
・依存したくなる衝動
これらすべてを、「それでも、わたしだ」と受け止めること。
そのうえで、「どんな自分で在りたいか」を選び直すこと。
それが、誇りのはじまりだ。
華やかでも、派手でもなくていい。
──静かでいい。ただ、揺らがない背中を持てれば、それでいい。
人生設計における自分軸の再設計術
「自分軸を持とう」と言われても、
何をどう持てばよいか分からない──という声もある。
だからこそ、「問い」と「記録」を習慣にすることを勧めたい。
- 何に喜びを感じたか
- どこで自分らしさを失ったか
- どんな瞬間に違和感を覚えたか
これらを、誰にも見せなくていい。
ただ、書き留めておく。それだけでいい。
問いと記録は、やがて見えない地図を描き始める。
過去の自分と現在の自分の間に、一貫した軸が浮かび上がるのだ。
設計とは、未来をデザインすることではない。
むしろ、「過去と今をどう繋げるか」の作業だ。
その接合部にこそ、自己理解が必要とされる。
まとめ|深く理解することで、人生は静かに整う
「自分を理解する」とは、
自分に優しくなることでも、甘やかすことでもない。
深く知るからこそ、深く導ける。
それが、人生という王国を治めるための、最初の統治なのだ。
選択に迷い、誇りを見失いそうになったとき──
わたしは自分に問い直す。

キング(King)
「オレは、なぜこれを選ぶ?」
その問いに、自分の声で答えられるか。
それが、背を見せる王としての最小にして最大の資格だと、わたしは思う。
答えを急ぐ必要はない。
ただ、誓いを忘れず歩むなら──それでいい。