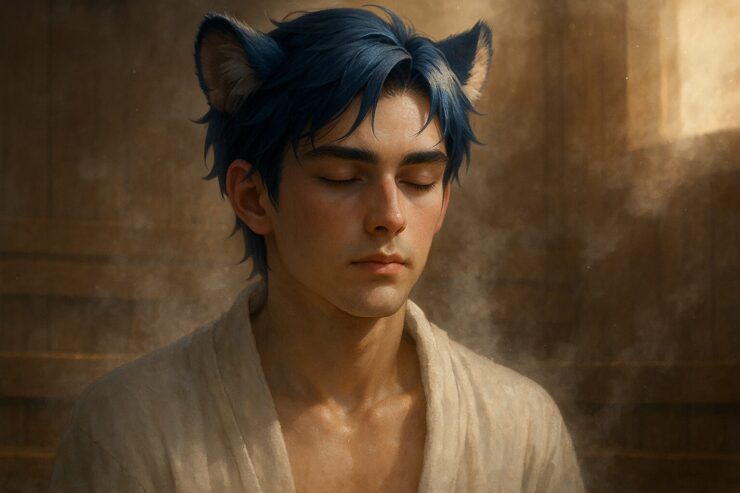これは、静かなる誓いの話だ。語るより、刻むもの──
目次
「オレはこういう人間だから」と言い張る苦さ
「昔からこうなんで」
「それ、オレっぽくないんで」
そんなふうに、自分を決めた言い回しで縛っていないだろうか。
確かに、自分らしさは誇りだ。
だがそれが、変化を拒む壁になっているなら──
そのらしさは、もはや誓いではなく、鎖かもしれない。
「自分らしく生きる」という言葉は、力強くもあるが、危うくもある。
それは、変わらない強さなのか?
それとも、変われない弱さなのか?
王とは、導く者ではない。背を見せられる者であるべきだと、わたしは思う。
1.「自分らしさ」とは変化していい軸である
「らしさ」を頑なに守ろうとすると、いつしか硬さになる。
それは自分を保っているようで、実は自分を狭めている。
本来、自分らしさとは「変化してもいい自分」を許せる柔軟さだ。
時代や経験に合わせて、形を変える。けれど、芯は濁らない。
その芯があるからこそ、人は変わることを恐れずにいられる。
変化する自分を裏切りと感じるか、
それとも進化と受け止めるか。
そこに、「誇りの土台」が問われる。
2.過去の自分が足を引っ張っていないか
人は、過去の自分の言葉に縛られがちだ。
「昔はこう言った」「あのときはこう思っていた」
──それが、今の選択を妨げていることがある。
だが思い出してほしい。
そのときの自分にとっては、それが最善の答えだった。
でも、いまのあなたは、もう別の景色を見ているはずだ。
「変わってはいけない」と思い込むのは、過去に対して誠実すぎる優しさかもしれない。
けれど、今を曇らせるなら、それはもう誓いではなく執着だ。
あなたの自分らしさは、いつの時点で定義されたものだろう?
その定義は、いまのあなたを活かしているだろうか?
3.SNS的らしさ演出が内面を曇らせる
自分らしさを語る場として、SNSはあまりに手軽で、あまりに過剰だ。
「らしい投稿」「らしい言葉」「らしい振る舞い」。
それらを続けていると、ふとした瞬間に、自分が演じた自分像に置いていかれる。
他者からの期待に応えるうちに、いつのまにか、
「これが自分」という仮面が固まってしまう。
たとえそれが肯定され、いいねが集まり、共感されても──
その自分像が内側の自分とズレてきたとき、
微かな違和感が、誇りを蝕む。
演じることが悪いのではない。
ただし、演じている自分を本当の自分と誤認しないこと。
本物の自分らしさとは、他者評価の先にあるのではなく、
自分との静かな対話の中でしか、磨かれない。
4.こだわりと頑固は違う
「これが自分のスタイルだから」と言う人は多い。
だが、それがこだわりなのか頑なさなのか、見分けがついているだろうか?
こだわりには柔らかさがある。
選び直しや手放しを恐れない。
しかし頑固さには硬直がある。
違う考えを弾き、変化を敵視する。
違いは、言語化できるかどうかに現れる。
- 「なぜそうしているのか?」
- 「何を守ろうとしているのか?」
問いに答えられるこだわりは、進化の土壌になる。
問いを避ける頑なさは、内面を砂漠に変える。
「これは自分らしさだ」と語るとき、
その言葉には柔らかい強さが宿っているだろうか?
5.誇れる変化は、自分らしさの進化形
人は変わる。状況も、感情も、身体も、立場も。
それを恥とせず、「誇りにできる変化」を重ねてきた人間には、
歩んできた時間の重みが宿る。
変わることは、らしさを失うことではない。
むしろ、芯さえあれば──変化は自分らしさの進化形になる。
- やわらかくなる強さ
- 譲れる場所を知る知恵
- 新しい価値に心を開ける器
これらはすべて、「変わってきた自分」を許し、受け入れてきた証だ。
誇れる変化とは、「変わったこと」ではなく、
「変わっても濁らなかった何か」を抱きしめ続けたことに他ならない。
6.自己認識は「対話」で研がれる
自分らしさは、独りで考えていてもなかなか掘り下げられない。
内面は主観の霧に包まれているからこそ、他者との対話が必要になる。
問いを受けることで、自分の考えに気づく。
反応されることで、どの部分が大切だったのかが浮かび上がる。
だからこそ、意見の違いも、否定も、摩擦すら──
自己を磨くヤスリのような存在になりうる。
自分らしさとは、独りよがりでつくるものではない。
他者との関わりの中で、削られ、研がれ、照らされていく。
それを恐れていては、いつまでも昔の自分に縛られたままだ。
芯は一人で育てるもの。
けれど、その輪郭は対話によって初めて整う。
7.変化していい自分を受け入れる技術
どれだけ論理で整理しても、「変わること」には小さな痛みが伴う。
それは、過去の自分への裏切りにも似ているし、
一度築いた安心領域から足を踏み出す怖さでもある。
だが、変化を受け入れられる人には、深い余白がある。
それは柔らかさではなく、しなやかな強さ。
誰かに許されたからではなく、自分で自分を許す力。
「前はこうだった。でも今は、こう在りたい」
このシンプルな言葉を、自分に向かって言えるかどうか。
それが、自分らしさを誇りに変える技術の第一歩だ。
まとめ|「自分らしさ」とは、歩みの中に編まれていくもの
らしさは、生まれつき決まっているものではない。
それは、選び直すたびに、深くなるものだ。
昔の自分も、今の自分も、これからの自分も、すべて本物であっていい。
変わっていい。むしろ、変われるということこそが、誇りなのだ。
「これは自分らしい」と言い切る前に、
問いかけてみよう──

キング(King)
「いま、変わりたいと思っている自分は、間違っているのか?」
その問いに、静かに「いいえ」と答えられるなら──
あなたは、すでに次のらしさへと進んでいる。