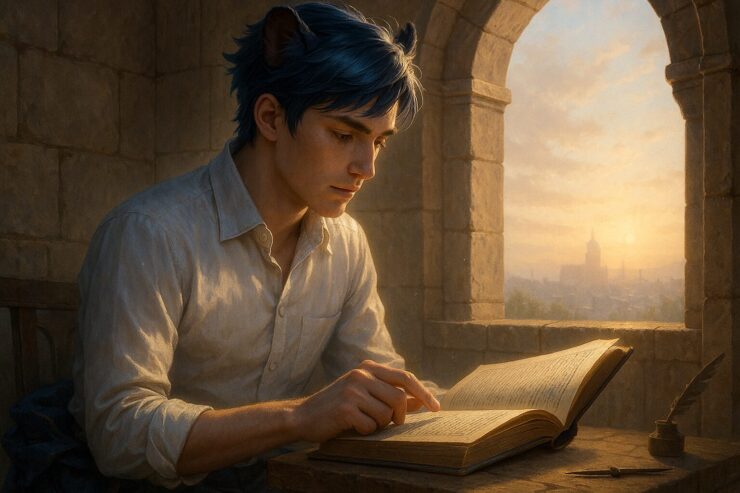成果は、積み上げてきた。
任された仕事も、ひとつずつ応えてきた。
──けれど、いざ「自分の強みは?」と問われると、言葉に詰まる。
なぜだろう。
評価は受けているのに、自信にはなっていない。
経験は重ねているのに、自分を語る言葉が見つからない。
それは、強みという言葉を、
どこか遠い才能のように捉えてしまっているからかもしれない。
強みとは、誰かに勝るためのものではない。
「背負う覚悟を持てること」こそが、その本質なのだ。
目次
「強み」は自己満足ではない
自己PRが苦手な人ほど、
「自分で自分を評価すること」に、どこか抵抗を感じている。
「強み=自画自賛」ではないか──
「自己満足で終わってしまうのではないか──」
だが、強みとは、他者との比較のために存在するものではない。
それは、「自分がどんなときに自然と力を発揮できるか」
「どんな状況でも手を離さずにいられるか」という、
内側の一貫性を知るための問いなのだ。
自己満足ではなく、自己信頼へ。
その静かな移行が、強みの輪郭を浮かび上がらせる。
「成果」より「視点の特徴」に注目
強みを探すとき、多くの人が「実績」や「評価された行動」を挙げる。
たしかにそれは、外側から見える成果だ。
けれど、本当の強みは、視点の持ち方に宿っている。
たとえば──
同じプロジェクトでも、数字を追う人もいれば、チームの空気に気を配る人もいる。
全体を俯瞰する人もいれば、細部を詰める人もいる。
それは意識せずに行っている、「視点の癖」=無意識の戦略だ。
成果は他人にも再現できるかもしれない。
だが、その視点は、あなた固有の設計図だと、わたしは思う。
他者評価と自己認識のズレを埋める
「自分では強みだと思っていなかったのに、なぜか周囲に評価された」
──そんな経験はないだろうか?
それは、他者の視点が、自分の無自覚な強みを見抜いていた証だ。
人は、自分の当たり前を疑わない。
だからこそ、自分では特別とも思っていない行動や考え方が、
他者にとっては「助けられた」と感じる要素になっていることがある。
自己認識と他者認識のズレに、強みの種がある。
だからこそ、信頼できる誰かにこう尋ねてみるといい。
「わたしの助けられたところって、どこだった?」と。
その答えはきっと、
あなたの誇りの起点になる。
「行動の癖」に宿る本質
強みは、意識して選んだスキルの中にはないことが多い。
それよりも──
繰り返される行動の癖の中にこそ、本質が宿っている。
・ミーティングで自然と全体を整える
・誰かがこぼした言葉を、さりげなく拾い直す
・無意識に、複数の視点を想定して話す
これらは「技術」ではない。
在り方に根ざした行動だ。
強みとは、意識せずに流れている内なる設計の痕跡。
その癖に気づいたとき、
自分自身が少し、誇らしく見えてくる。
「過去の共通点」が軸になる
人生を振り返ると、
どんな場所にいても、自然と引き受けていた役割がある。
・いつも人の相談役になっていた
・調整役やまとめ役を任されることが多かった
・気づけば、影で誰かを支えるポジションにいた
それらは偶然ではない。
わたしが自然と背負えるものが、そこに現れている。
過去を並べて、その共通項を拾う。
すると、そこに静かな軸が立ち上がってくる。
強みとは、すでに持っていたものに気づく行為なのだ。
「強み」は引き受ける覚悟で完成する
強みは見つけるだけでは不十分だ。
「引き受ける覚悟」がなければ、それは単なる資質に過ぎない。
たとえば──
「調整が得意です」と言うのは簡単だ。
だが、いざ対立が起きた場面で、摩擦を引き受け、
誰も触れたがらない中心に立てるかどうか。
そこに、「覚悟としての強み」が問われる。
わたしは思う。
強みとは、背負ってでもやり遂げたいことの輪郭そのものだと。
それを引き受けることで、
初めて、強みは誇りに変わる。
本質は「何に誇りを持てるか」
強みを知るというのは、
能力を誇ることではない。
それはむしろ──
「自分は、何に誇りを感じる人間なのか?」を問い直す行為だ。
数字を達成した瞬間かもしれない。
仲間を陰で支えたときかもしれない。
失敗から立ち上がった日かもしれない。
どんな瞬間に「これが自分だ」と感じたか──
そこに、誇りの火種としての強みがある。
だからこそ、強みとは他人と比べるものではなく、
自分が大切にしたい在り方を映す鏡なのだ。
「言葉にする力」が信頼をつくる
どれだけ強みを持っていても、
それが言葉になっていなければ、伝わらない。
そして、伝わらなければ、信頼は育たない。
「わたしは、こういう視点を大切にしている」
「こんな場面で、自分の力が活きると感じている」
たとえ拙くてもいい。
言葉にしようとする姿勢そのものが、信頼を生む。
それは、誇りを外に置くのではなく、
誇りを自分の手で掲げるための小さな技術だ。
だから、今日からほんの少しずつ、
自分の強みを「言葉で持ち歩く」習慣をはじめてみよう。
答えを急ぐ必要はない。ただ、誓いを忘れず歩むなら──それでいい。
自分の強みが分からない──
そう感じてしまうのは、
きっと、あなたが「言葉に真剣であろうとする人」だからだ。
誇張せず、盛らず、背伸びせず、
本当の自分を、自分で見つけたいと願っているから。
それは、弱さではない。
それは、誇りを探す誠実な問いだ。
だから、焦らなくていい。
言葉にしては消え、また拾い直すその繰り返しの中で、
やがてきっと、あなたにしかない強みが浮かび上がってくる。
わたしは、そう信じている。