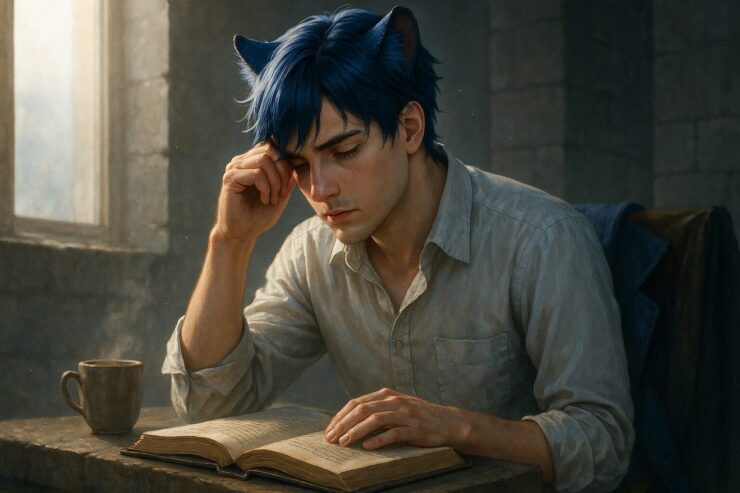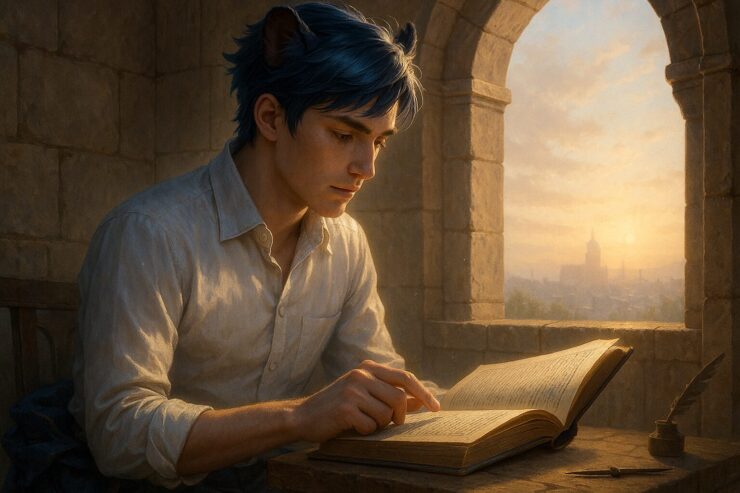王とは、導く者ではない。背を見せられる者であるべきだと、わたしは思う。
評価されたいと思うのは、自然なことだ。
けれど、それが勝ち負けでしか測られなくなったとき──
どこかで、心がすり減っていく。
上に行くこと。
抜きん出ること。
他より多く、早く、強くあること。
その競争の中で疲れ果てた者は、
やがて「何のために頑張っているのか」が見えなくなる。
わたしは思う。
誇りとは、誰かに勝つことで宿るものではない。
それは、自分の基準で生きる覚悟から生まれるものだ。
目次
「勝ち負け」が曖昧になる時代
かつては、順位や実績、数字がすべてだった。
「勝った者」が正しく、「負けた者」は悔しさを糧に立ち上がった。
だが──
今、その勝ちが曖昧になってきている。
・SNSのフォロワー数
・年収
・職位
・ライフスタイル
どれも数値で比較できるようでいて、
人それぞれの価値観が混ざり合い、もはや単純な優劣では語れなくなっている。
そんな時代において、
「勝ちたい」という言葉の重みも、
「勝つ意味」そのものも、静かに問い直されはじめている。
「他者軸」の評価は安定しない
他者と比べて得た評価は、
一見、わかりやすく、誇らしく見える。
だが──
それは外側に置かれた誇りであり、
いつでも他者の変化に揺さぶられてしまう。
誰かが追い越せば、価値が下がる。
基準が変われば、見られ方も変わる。
どこまで行っても、「もっと」が終わらない。
わたしは思う。
安定した誇りは、自分の内側にしか築けない。
他者軸を捨てることは難しい。
だが、その先にしか、
静かに揺るがない軸は現れない。
「比較疲れ」から自由になる方法
比較は、自然に始まる。
他人の成果、年齢、立場、生活ぶり──
気づけば、自分を誰かと並べて見ている。
だが、その比較が習慣になったとき、
人は満たされなさの中に居続けることになる。
どれだけ成果を出しても、
誰かの「もっと」を見れば、心が揺らぐ。
そこから抜け出す第一歩は、
「評価の起点」を他者ではなく、自分の問いに戻すこと。
「わたしは、どうありたいのか?」
この問いを持つ者だけが、比較から自由になれる。
「貢献」という軸へのシフト
勝ち負けの軸は、他人との対立を前提としている。
だが、貢献の軸は、他者との共存を前提にしている。
・この仕事は、誰を支えているか
・自分の存在が、何を助けているか
・今日の行動に、誰かの笑顔が結びついているか
こうした問いに向き合うと、
競争とは異なる「実感」が心に残る。
それは、数字では測れないが、
深度で残る価値だと、わたしは思う。
貢献という軸を持ったとき、
人は自然と、誇りと調和を身にまとうようになる。
「誰のために動けるか」が価値になる
評価とは、単に「何をしたか」ではない。
「誰のために動けたか」でこそ、深まるものだ。
ある人は、数字のために動く。
ある人は、上司の期待のために動く。
──そして、ある人は、仲間や未来の誰かのために動く。
誰のために力を注ぐか。
その相手の選び方に、
その人の価値観と器のすべてが宿る。
わたしは、そう信じている。
だから、自分に問いたい。
「わたしは、誰のために歩いているのか?」と。
「主語」を変えることで見える自分
キャリアの話になると、
「会社が」「上司が」「市場が」──
と、外の主語で語られることが多い。
だが、自分の人生において、
主語を取り戻さねばならない。
「わたしは、こうしたい」
「わたしは、こう在りたい」
この主語の変更だけで、
思考の構造が変わり、
選択の軸が整い始める。
勝ち負けを脱するとは、
「主語をわたしに戻すこと」でもある。
そこから、誇りが再起動する。
「意味」と「納得感」の再定義
人は、「評価されること」で頑張れる。
だが、「意味を見いだせること」で長く続けられる。
勝ち負けの軸では、評価の結果は「他者の判断」だ。
けれど、意味の軸では、判断は「自分の問いと納得」だ。
「これは、わたしが誇れることか」
「この働き方は、自分の在りたい姿につながっているか」
──その問いに静かにうなずけるなら、
たとえ誰にも褒められなくても、
内なる納得感が、歩みを支えてくれる。
意味の再定義とは、
「外から与えられた基準」をそっと手放し、
自分の人生を自分で選び取る作業なのだ。
「わたし基準」の誇りを育てる
評価は外にあるもの。
だが、誇りは、内に育てるものだ。
わたしはこれまで、
勝たなければ意味がないと思っていた。
成果がすべてだと信じていた。
だが、いつからか気づいた。
「誰にも見えなくても、守りたい自分」がある。
それが「わたし基準の誇り」だ。
数字で示せない、
他人には伝わらないかもしれない、
けれど、わたしの火種になってくれるもの。
それを胸に抱き、
静かに進んでいける者が、最も強いと、わたしは信じている。
答えを急ぐ必要はない。ただ、誓いを忘れず歩むなら──それでいい。
評価されたい。認められたい。
──その願いを否定する必要はない。
けれど、その評価が「勝ち負け」だけで決まるのなら、
わたしたちは、いつまでも安らぐことができない。
だからこそ、誇りの軸を、自分の内に育てていくこと。
比較ではなく、貢献へ。
勝敗ではなく、意味と納得へ。
他人の言葉ではなく、自分の主語へ。
その静かな移行が、
人生に揺るぎなき誓いを宿していく。
わたしは、そう信じている。